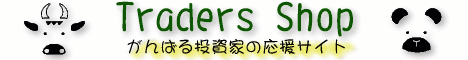
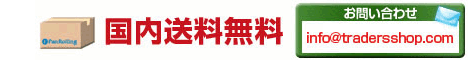
| 携帯版 |
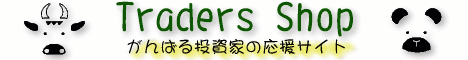
|
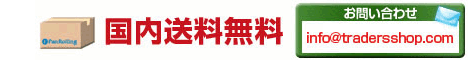
|
|
フィスコ投資ニュース配信日時: 2025/10/27 17:31, 提供元: フィスコ ミネベアミツミ:精密技術と量産力で世界を支える「相合」精密部品メーカー、株価の上値余地大きい*17:31JST ミネベアミツミ:精密技術と量産力で世界を支える「相合」精密部品メーカー、株価の上値余地大きいミネベアミツミ<6479>は、ベアリングなどの機械加工品事業、半導体、小型モーター、電子デバイスなどの電子機器事業、自動車部品・産業機械・住宅機器事業を手掛ける超精密部品メーカーである。ミニチュア・小径ボールベアリングで世界シェア約60%を誇り、外径22mm以下の精密軸受で他社の追随を許さない。月産約4億個超という圧倒的規模の生産キャパシティを持ち、製造装置の多くを自社開発することで、高精度とローコストを両立させている。ベアリングの外輪・内輪間にボールを組み込み、摩擦を軽減するこの部品は、回転を伴うあらゆる機器に欠かせない。精密な球体加工と加工公差の制御が品質を左右するが、同社はこの分野で長年にわたり技術的優位を築いてきた。そのほか、HDD(ハードディスクドライブ)用ピボットアッセンブリーの世界シェア90%、1直リチウムイオン電池用保護IC80%とグローバルマーケットの中でニッチ分野に特化し、高いシェアを獲得。売上高に対する世界シェアNo.1製品の割合は50%を占めている。 事業セグメントは、プレシジョンテクノロジーズ(PT)、モーター・ライティング&センシング(MLS)、セミコンダクタ&エレクトロニクス(SE)、アクセスソリューションズ(AS)の4つに大別される。PT(2025年3月期売上高構成比16.8%)とMLS(同26.8%)は旧ミネベアの超精密加工技術、大量生産技術を核とした機械加工・電子部品事業である。SE(同34.7%)は旧ミツミ電機を源流とする半導体・電子部品事業で、個別顧客仕様に対応するアナログ半導体や光デバイスを中心に展開する。AS(同21.5%)は旧ユーシンなどを中心とする自動車部品領域で、ドアハンドル・ミラーといった車載コンポーネントをTier1として供給している。各セグメントに国内外の競合が一定存在するが、同社は「超精密×大量生産」という製造業としての二軸の強みによって差別化している。ベアリングでは中国メーカーとも競合するが、微細な加工精度と量産安定性において群を抜く。半導体では顧客個別ニーズに対応したニッチ市場で高収益を確保している。 2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高366,925百万円(前年同期比3.2%増)、営業利益17,432百万円(同7.8%減)となり、売上は1Qとして過去最高を更新。売上高、営業利益とも計画を上回る着地となったようだ。セグメント別では、PTが高い収益力を維持した。データセンター向けファンモーター用途がボールベアリング外販数量の約3分の1を占め、AIサーバー需要の拡大を背景に数量好調。航空機向け需要も中長期的には回復基調にあり、エアバスやボーイングの生産増が追い風となっている。MLSはHDDスピンドルモーターやバッテリー保護モジュールが牽引する一方、自動車向けモーターはコンテンツグロース(搭載点数増加)により、自動車生産台数伸び悩みの影響を最小限に抑えた。SEは増収減益となり、スマートフォン向けカメラモジュールやゲーム機向け組立などサブコア事業は低採算だが、アナログ・パワー半導体領域では20%前後の利益率を確保している。ASは減収減益となり、世界的な自動車生産調整の影響でトップラインは停滞したが、コスト改善と製品の高付加価値化を進めている。そのほか、米相互関税15%の前提において、1Qは直接・間接ともに業績影響は軽微だったようだ。通期業績見通しはリスクシナリオを引き上げており、ベースシナリオは売上高1,520,000百万円、営業利益100,000百万円、純利益71,000百万円を据え置いている。 市場環境面では、1973年から2026年にかけて世界のGDPがCAGR6%成長するなか、同社のベアリング生産数量は約2900倍かつCAGR16.2%成長を遂げてきた。今後も、生成AIなどによるデータ量の拡大、ロボティクス技術の発達、モビリティの発展が進む中で、世界のGDPの成長に伴って市場の1人当たりの可処分所得が上がり、高級機能製品が売れ、高級部品の必然性は高まっていく。なかでも、直近はデータセンター投資が拡大しているが、サーバー出荷台数CAGR19.8%成長、ファンモーター市場CAGR17.9%成長とされ、同社のベアリング・モーター需要も長期的に拡大が見込まれる。航空機需要回復やEV部品のコンテンツ増もプラス要因となろう。 中期経営計画では、8本の成長領域(ベアリング、モーター、アナログ半導体、アクセス製品、センサー、コネクタ・スイッチ、電源、無線・通信・ソフトウェア)のうち4本を確定事業と位置づけ、残る4本の確定化を目指す。利益構造の高度化に向けては営業改革を推進し、案件ごとの利益可視化とインセンティブ制度の導入を進めている。成長ドライバーとして「ヒューマノイド」「ドローン」「自動運転」を掲げ、いずれも精密部品やセンシング技術などを活かせる領域として注力中。とりわけヒューマノイドロボット向け部品では、関節駆動やセンサー系で既存製品群をパッケージ供給できる点を強みとしている。11月下旬にはIRデーを開催し、これら新成長領域の定量目標を提示予定としており、非常に注目しておきたいところ。 株主還元については、中期的なキャッシュアロケーションポリシーに基づき、安定した配当を実施している。フリーキャッシュフローの50%還元を基本方針とし、配当性向30%程度を目線に置く。自己株式取得についても選択肢としつつ、資本構成を考慮しながら機動的に対応する姿勢を示している。 総括すると、ミネベアミツミは超精密加工と大量生産技術を軸に、ベアリング・モーター・半導体といった異なる事業群を「相合」によって有機的に連携させる総合精密部品メーカーである。AI・データセンター・EVといった構造的成長領域への露出が高く、足元業績も安定して推移。今後はヒューマノイドやドローンなど新分野への展開が本格化し、コングロマリットディスカウントの解消余地を内包する。株価は昨年7月高値3799円から乖離があり、上値余地がのこっているなか、精密技術とグローバル量産力を兼ね備えたグローバルニッチトップ企業として今後の動向に注目しておきたい。 《FA》 記事一覧 |